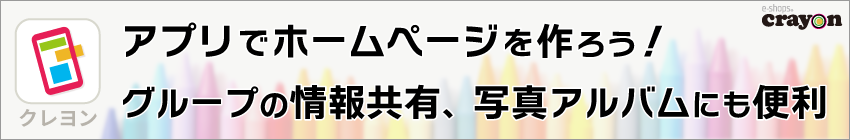被害者の皆さんへ
S塾被害者の会は、オーナーと元オーナーの有志により設立されました。学習塾の特徴は、教育ニーズの移り変わりによって多様化しています。以前は講師1人に生徒数十人といった集団での授業が主流でした。現在は、生徒のレベルにあわせた教育へのニーズが高まり、個別も増加しています。英語の必修化・プログラミングの需要の高まりなどもあり、対応する塾も増えています。
塾経営を成功させるには、業界全体の現状を正しく把握し、今後の動向に考えを巡らせることが重要です。具体的には塾業界の市場規模などのデータを分析し、学習塾経営の今後を考察していくことです。加速する少子化により学習塾業界の売上低下が予測されていた一方、現状としては売上は増加し市場規模は拡大し続けています(参照:経済産業省 特定サービス産業動態統計調査)。私立中学受験がブームとなり、小学生の月謝単価が上昇しているのです。そもそも塾とは、義務教育課程または高等教育以上の課程にある児童・生徒に対して、学習・進学指導を行う教育施設です。教育施設といっても公教育とは別で、私的な教育システムとして経営されています。「日本標準産業分類」でも、現代の学習塾は以下のように定義づけられています。「 小学生、中学生、高校生などを対象として学校教育の補習教育又は学習指導を行う事業所」 ※総務省「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」より引用
しかし、学習塾の倒産が増加しています。学習塾業界の市場規模が拡大しているとはいえ、参入しやすい状況とは言えない状況です。2024年上半期だけでも倒産塾数は26件にも達し、業界の負債総額も過去最高となりました。(参照:東京商工リサーチ)
S塾も閉校が止まりません。要因の多くは「販売不振」。市場のニーズが多様化する一方、FC本部に従うしかなく、大手のように柔軟な対応ができずに淘汰されてしまった教室が多いと考えられます。
では、加盟者に経営能力が欠如しているのでしょうか。いえ、そうとは言えません。自由な運営ができませんから。
ご案内
このサイトでは、
・加盟希望者が契約を締結するかどうかの判断に重要と思われる情報を提示していきます。
・現役加盟者に有益な情報の共有の場を提供します。
・元加盟者の入会、本部スタッフの内部告発も歓迎しています。
・校舎運営の支援を実施しています。
運営一覧
 トピックス・ニュース
トピックス・ニュース- 2025/6/5 新橋にて新規ご入会者様と懇親会
- 2025/5/28 法律勉強会を開催。
- 2025/3/26 五反田にて懇親会を開催しました。
- 2025/2/27 3月10日に専門家によるAI勉強会を開催します。
- 2025/2/12 T・M様 新規ご入会ありがとうございます
- 2025/2/8 新規FC加盟検討者向け相談会(静岡県)無事に終了しました。今回は3名の参加でした。
- 2025/1/14 T・K様 新規ご入会ありがとうございます。
- 2025/1/13 Y・T様 新規ご入会ありがとうございます。